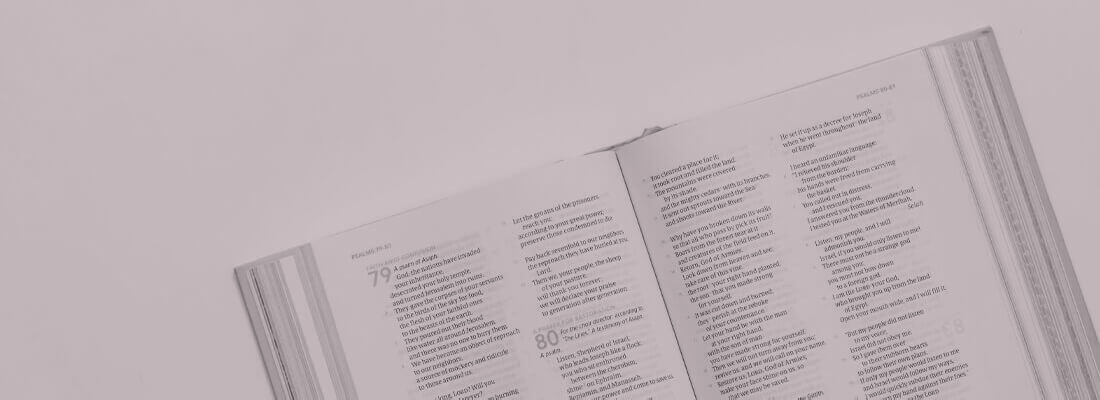今回は「競合他社の戦略的な特性を把握し、自社の戦略改善に役立つ方法」をテーマにお伝えしていきます。

ライバル調査のポイント
ライバルを明確にしたら、次はライバル調査です。
しかし、ただ漫然とライバルのチラシやホームページを眺めていても表面的なことしか見えてきません。
・商品力
・地域
・客層
・集客方法
・紹介入手方法
の5つのポイントで戦略的な意図をチェックしていくと色々なことに気がつくはずです。
「文字を大きく手描きにしているのは、高齢者を狙っているからか」とか、「写真を大きくビジュアル優先しているのは、デザイン志向の顧客を意識しているからか」など自分でもさまざまな分析・検討ができるようになっていくと思います。
これが逆に、「手描きの文字にすればいい」「写真を大きくすればいい」と目先のことだけ取り入れても、自社の方針と合わなければ当然効果は望めません。
目的(戦略)があっての手段なのですから。
また、人の戦略はよくわかるし、勉強になります。
うまくいっている会社ほど、エリアも顧客層もよく絞られていて特徴的ですからね。
他社のやり方から戦略の立て方を学ぶといいでしょう。
最高の実践的な参考書です。
叩き台があると「自社ならこうする」と考えを展開させやすいですしね。
他社の動向に刺激を受けて、こちらのモチベーションも高まる、というメリットもありますよ。
ライバル調査において手がかりにしやすいのが、見学会やイベントなどを告知するチラシです。
チラシを撒く回数や頻度、配布するエリアを調べるだけでも、ライバルの戦略的な特性が明確に把握できます。
とくに力を入れているエリアと、そうでもないエリアとの線引きが見えてくるはずです。

営業戦略上、エリアの概念はとても重要です。
手元に地図を用意して、いつでも開けるようにしておきたいもの。
いまは町名変更などで「地元」の意識もわかりにくくなっていますが、幹線道路や河川、線路などで自然と人の流れは区切られているものです。
直線距離としてはA社のほうに近くても、その経路で大きな道路を渡るとなると、心理的な距離感は倍増されます。
自社と他社のエリアを検討するうえでは、そうした地形についても視野に入れたほうがいいでしょう。
チラシを集めるには、自社のスタッフや協力業者、友人・知人のほか、OB顧客などにもお願いするといいでしょう。
最近は各社ともエリアを絞ってきている傾向があります。
半年に1回くらいは調べて状況を更新していくことをお勧めします。
あと自社から1㎞圏内くらいは実際に歩き回ってみてください。
予想以上に多くの会社の工事現場があることに気がつくはずです。
本来、自社が守るべき地盤に進出してきている会社については、しっかりマークしておきたいですね。
他社のホームページも調査の材料になります。
ライバルがターゲットにしている具体的な地名や町名、得意とする工法・部材・スタイル、客層などがしっかり記載されているはずですからね。
施工事例の写真を見ると受注の傾向もわかります。
ブログのほか、facebookなどのSNSを使う会社も増えてきましたね。
ライバル他社の社長やスタッフがどこで工事しているのか、どのようなことを考えているのか、近況をアップしてくれていますからチェックしておかない手はありません。
投稿者プロフィール

-
1962年 大阪生まれ。1位づくり戦略コンサルタント。
中小企業に従事した自らの体験を踏まえ、コンサルタントとしてこれまで1300社以上の指導実績を持つ。
また豊富な現場経験から生み出された1位づくり戦略をはじめ多彩なテーマで年間100回以上のセミナーを行い、実践的かつ即効性がある好評を博している。
自ら主催する経営塾「あきない道場」には、全国からたくさんの経営者が参加。その理論を実践し短期間に多くの成功事例を生み出している。
著書には、『小さな会社★採用のルール』をはじめ、『「あなたのところから買いたい」とお客に言われる小さな会社』、『小さな会社☆No.1のルール』、『小さな会社☆集客のルール』、『スゴい仕掛け』など、いずれもAmazonカテゴリーで1位を獲得している。
最新の投稿
 佐藤元相のブログ2024.6.18フォロワー1万人達成!マンダラチャートで計画したインスタライブ成功術
佐藤元相のブログ2024.6.18フォロワー1万人達成!マンダラチャートで計画したインスタライブ成功術 佐藤元相のブログ2024.5.27大阪城の御座船でユニークな新入社員入社式
佐藤元相のブログ2024.5.27大阪城の御座船でユニークな新入社員入社式 佐藤元相のブログ2024.4.26地域密着型の工務店が「ちょっと困った」リストを集めて受注、紹介を増やす取り組み
佐藤元相のブログ2024.4.26地域密着型の工務店が「ちょっと困った」リストを集めて受注、紹介を増やす取り組み 佐藤元相のブログ2024.3.18小さな会社の短期インターンシップ/事例紹介
佐藤元相のブログ2024.3.18小さな会社の短期インターンシップ/事例紹介